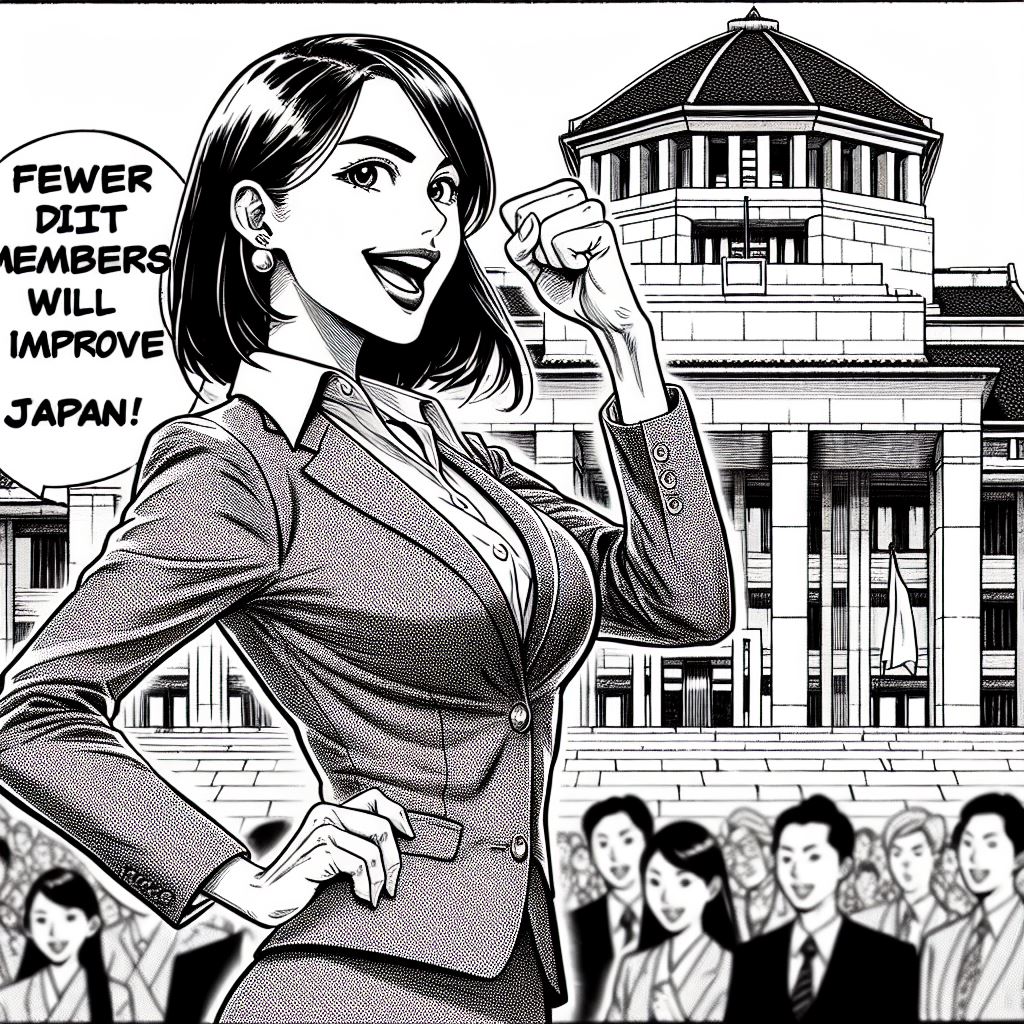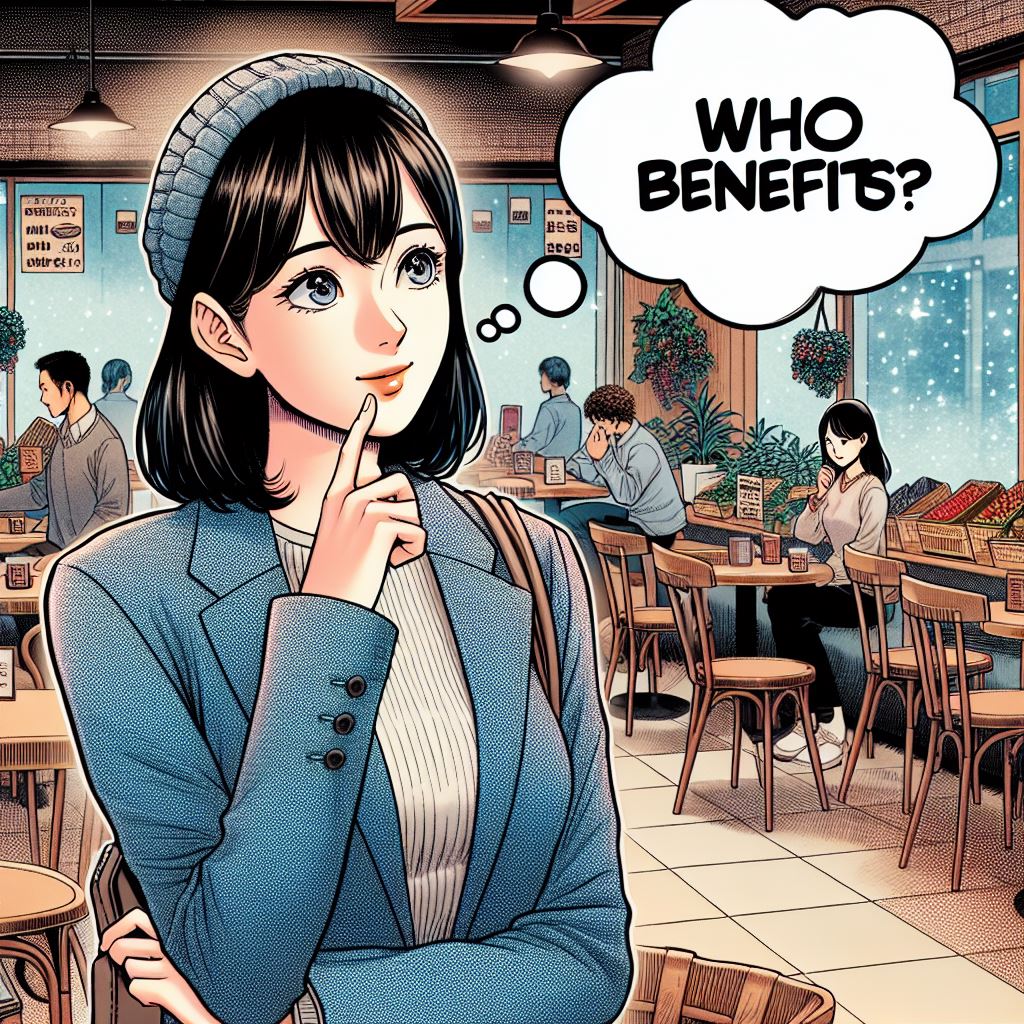-

日本を劇的に良くする政策:国会議員を都道府県代表47人に削減する案
日本は少子高齢化や人口減少という深刻な課題に直面しています。これに伴い、国会議員の数を見直し、現行の513人から都道府県代表の47人に削減することで、効率的で持続可能な政治システムを構築することを提案します。本記事では、議員削減の必要性を根拠... -

教養がある人の特徴とは?6つの行動から学ぶ「本当の品格」とは
「教養がある人」と聞いて、あなたはどんな人を思い浮かべますか?本をたくさん読んでいる人?知識が豊富で会話が上手な人?確かにそれらも教養の一部かもしれません。しかし、真に教養がある人とは、知識だけでなく、行動や言葉に人としての品格が表れて... -

日本政治への不信感と克服への道筋:透明性の欠如が招く国民の不満を解消するために必要な改革とは
1. 日本政治への不信感の現状 近年、日本の政治に対する国民の不信感が高まっています。その根本には、以下のような問題が指摘されています: • 透明性の欠如:意思決定プロセスや政策立案の過程が不明瞭で、国民が納得できる形で説明されていない。 • 政... -

なぜ補助金政策が選ばれるのか:再エネ賦課金や減税よりも優先される背景を探る
ニュースなどで「電気料金を補助金で支援する」という政策が発表されると、「もっと根本的に解決する方法があるのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。たとえば、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電を支援するための追加料金)の廃止や、直接... -

物価高騰と所得停滞――「得をしているのは誰か」とその裏付け
日本では近年、物価が上昇しているにもかかわらず、時給や月給の上昇が追いつかない現状が続いています。多くの消費者や労働者が生活の苦しさを感じる一方で、「この状況で得をしている者がいるのではないか」という意見も少なくありません。本記事では以... -

外国人が事件事故を起こしても不起訴になるのはなぜ?戦後日本の知られざる法の裏側!占領期の司法制度の闇とは?
今回は、意外と知られていない「戦後日本の司法制度の裏側」について、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。特に、占領期に起きた特殊な法制度の変化について、現代にも残る影響を含めて、じっくりとお話ししていきますね。 1. そもそも戦... -

若手官僚が直面する「やりがい搾取」の現実とは?国家公務員という仕事の光と影
夢を抱いて飛び込んだ官僚の世界 日本の行政を支える国家公務員。その中でも、厚生労働省など主要省庁の若手官僚たちは、国家の未来を背負う重要な役割を担っています。大学時代、社会のために役立ちたい、国家運営の最前線で活躍したいという強い思いを抱... -

政府の給付金支給政策とその問題点:本当に必要な支援とは?
昨今の物価高対策として、政府が住民税非課税世帯に対し給付金を支給する政策が注目されています。しかしながら、これは必ずしも公平な政策とは言えない側面も多く、実際に働いて納税している中間層に対して「不公平感」を与えているのが現状です。本記事... -

税金なんて一円も使わなくたって国民のマインドを変えれば経済成長はできる
「税金を減らし、国民の意識を変えることで経済成長を図る」というアイデアについて、詳しく解説していきます。この記事では、いかにして既存の仕組みを変えることで効率的な成長が可能なのか、具体的な施策とその効果についてお話しします。 1. 既得権益... -

財務省と日本経済の30年 – なぜ日本は世界第2位から転落したのか
かつて「Japan as No.1」と呼ばれ、世界第2位の経済大国だった日本。しかし現在、一人当たりGDPは世界32位まで転落しています。なぜこのような事態になったのでしょうか? 本記事では、日本経済衰退の背景にある財務省(旧大蔵省)の政策決定と、その影響...